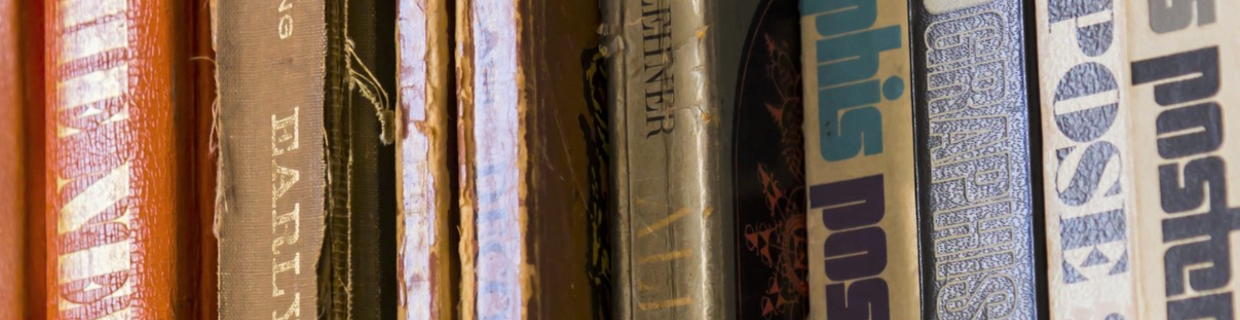古物営業について
■ 古物営業とは
古物営業とは、主に古物(中古品)を売買、交換、または他人の委託を受けて売買・交換を行う事業を指します。古物営業法によれば、古物営業は以下の3類型に分類されます。
① 1号営業(古物商)
古物を売買、交換、または委託を受けて売買・交換する営業
② 2号営業(古物市場主)
古物商間の古物の売買または交換のための市場を経営する営業
③ 3号営業(古物競りあっせん業者)
インターネットオークションなどで、古物の売買をしようとする人のあっせんをホームページを使用するせりの方法により行う営業。
リサイクルショップやバザー、フリーマーケットでの取引が古物営業に該当するかどうかは、その取引の実態や営利性などに照らして個別具体的に判断する必要があります。
なお、すべての中古品の売買が古物営業に該当するわけではありません。例えば、
・古物を売却することのみを行う場合
・自己が売却した物品を売却した相手方から直接買い戻す場合
これらは古物営業には当たりません。
古物営業法の目的は、盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図り、窃盗その他の犯罪の防止および被害の迅速な回復に資することです。古物営業を行うためには、都道府県公安委員会の許可が必要です。古物商には、取引記録の保存や身分証明書の確認などのルールを守ることが求められています。無許可で中古品の転売ビジネスを行うと、古物営業法違反として警察に逮捕される可能性があります。
■古物とは
古物営業法において、古物とは以下の3つのカテゴリーに分類されます。
① 一度使用された物品(中古品)
「使用」とは、その物本来の目的に従ってこれを使うこと
衣類…着用すること、自動車…運行すること、美術品…鑑賞すること
② 使用されない物品で使用のために取引されたもの(新品であっても、一度消費者の手に渡り、使用のために取引された物品)
③ これらの物品に幾分の手入れをしたもの(①または②の物品本来の性質や用途に変化を及ぼさない形で修理等を施したもの)
古物の範囲は広く、小さな電子部品やアクセサリーから、大型のバス、鉄道車両、住宅、船舶まで、様々な物品が含まれます。
ただし、以下のような大型機械類は古物から除外されています。
・総トン数が20トン以上の船舶
・航空機
・鉄道車両
・重量が1トンを超え、建造物に固定された機械
・重量が5トンを超え、自走できない機械
■古物商の形態
①店舗を設けて行う
②インターネットを利用して行う
③行商(特定の店舗を持たず商品を顧客がいるところへ運び販売をすること)により行う
これらのいずれも行わない場合は、古物商を行うことはできません。
■古物営業の具体的な例
古物営業の具体的な例には以下のようなものがあります:
① リサイクルショップ:中古品全般を扱う最も一般的な古物営業の形態です。
② 中古書店:古本や中古の雑誌などを販売する店舗です。
③ 中古CDショップ:中古の音楽CDやDVDなどを扱う店舗です。
④ 中古家電店:使用済みの電化製品を販売する店舗です。
⑤ 金券ショップ:使用済みの商品券や切符などを取り扱う店舗です。
その他にも、以下のような業態が古物営業に該当します:
⑥ 古物を買い取って修理や改修を行い、再販売する業者
⑦ 古物を買い取り、使用可能な部品のみを販売する業者
⑧ 古物の委託販売を行う業者(売却後に手数料を受け取る形態)
⑨ 古物を別の物と交換する業者
⑩ 古物を買い取ってレンタル事業を行う業者
⑪ 国内で購入した古物を海外に輸出して販売する業者
これらの業態は、古物営業法で定められた13種類の古物区分(美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付き自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品等、書籍、金券類)のいずれかに該当します。
古物営業を行う際は、これらの例を参考にしつつ、取り扱う商品や業態が古物営業法の規定に該当するかどうかを確認し、必要に応じて古物商許可を取得することが必要です。
■古物商になれない人(人的欠格事由)
古物商許可を取得できない人、つまり欠格事由に該当する人は以下のとおり。
① 成年被後見人、被保佐人、または復権を得ていない破産者
② 以下の刑罰を受け、その刑の執行が終わってから、または執行を受けることがなくなった日から5年が経過していない者
・禁錮以上の刑に処された者(罪種を問わず)
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等の有償譲受けなどで罰金刑を受けた者
・古物営業法違反(無許可営業、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反)で罰金刑を受けた者
③ 暴力団員またはその関係者
④ 住居の定まらない者
⑤ 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過していない者
⑥ 心身の故障により古物商等の業務を適正に実施することができない者
⑦ 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(例外:法定代理人から営業を許可されている場合、婚姻により成年と同一の能力を獲得している場合)
⑧ 営業所ごとに適切な管理者を選任できないと認められる相当な理由がある者
⑨ 法人の場合、役員にこれらの欠格事由に該当する者がいる法人
これらの欠格事由に該当する場合、古物商許可を取得することはできません。また、すでに許可を持っている古物商でも、これらの事由に該当するようになった場合は、許可が取り消される可能性があります。
■古物営業法の罰則
古物営業法には、違反行為に対して厳しい罰則が規定されています。
① 3年以下の懲役または100万円以下の罰金
・無許可で古物営業を行った場合
・偽りその他不正の手段で古物商の許可を受けた場合
・名義貸しを行った場合
・公安委員会の営業停止命令に違反して営業を続けた場合
② 1年以下の懲役または50万円以下の罰金
営業所または取引相手の住所・居所以外の場所で古物の取引を行った場合
③ 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・届出なしで仮設店舗で古物営業を行った場合
・取引相手の身元確認を怠った場合
・帳簿を3年以内に破棄した場合
・品触れに相当する古物について警察に届け出なかった場合
・必要な帳簿をつけていない、または虚偽の記録をした場合
④ 20万円以下の罰金
古物商許可申請書や添付書類に虚偽の記載をして提出した場合
⑤ 10万円以下の罰金
・行商時に許可証を携帯しなかった場合
・営業所の名称・所在地変更時に必要な届出をしなかった場合
・古物商の氏名、住所、取り扱う古物の区分、管理者の変更時に届出をしなかった場合
これらの罰則は、状況によっては懲役と罰金が併科される可能性もあります。
さらに、無許可営業や名義貸し、営業停止命令違反などの重大な違反の場合、許可の取り消しという行政処分を受ける可能性もあります。許可が取り消された場合、5年間は新たに古物商許可を取得することができません。
■まとめ
古物営業に当たっては、古物の売買を行うものであるか、扱う物は古物営業法に定められている古物に該当するか、古物を扱う形態はどのようなものか、古物商の人的欠格事由に該当しないか、について確認のうえ、警察から古物営業の許可を得る必要があります。